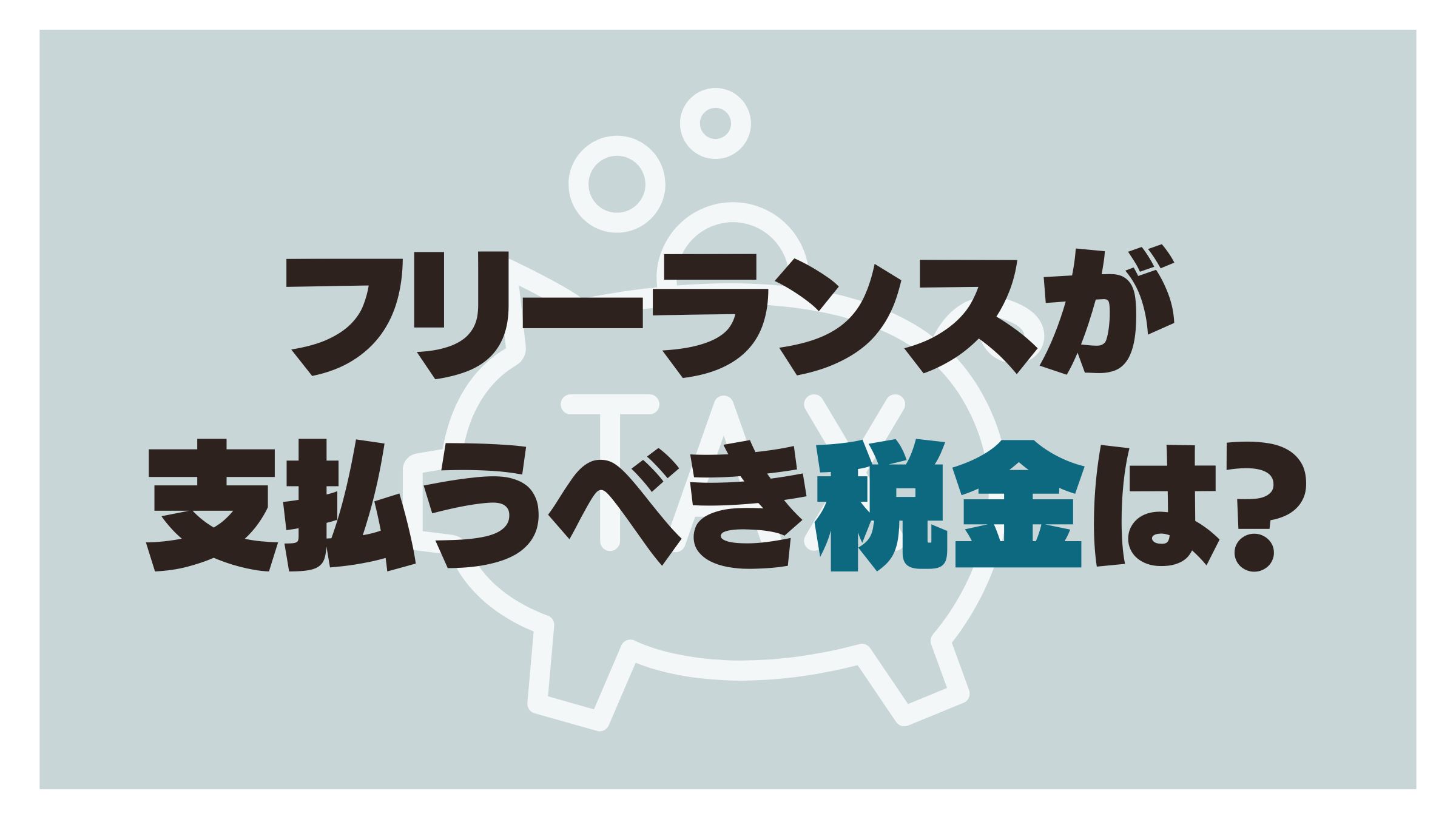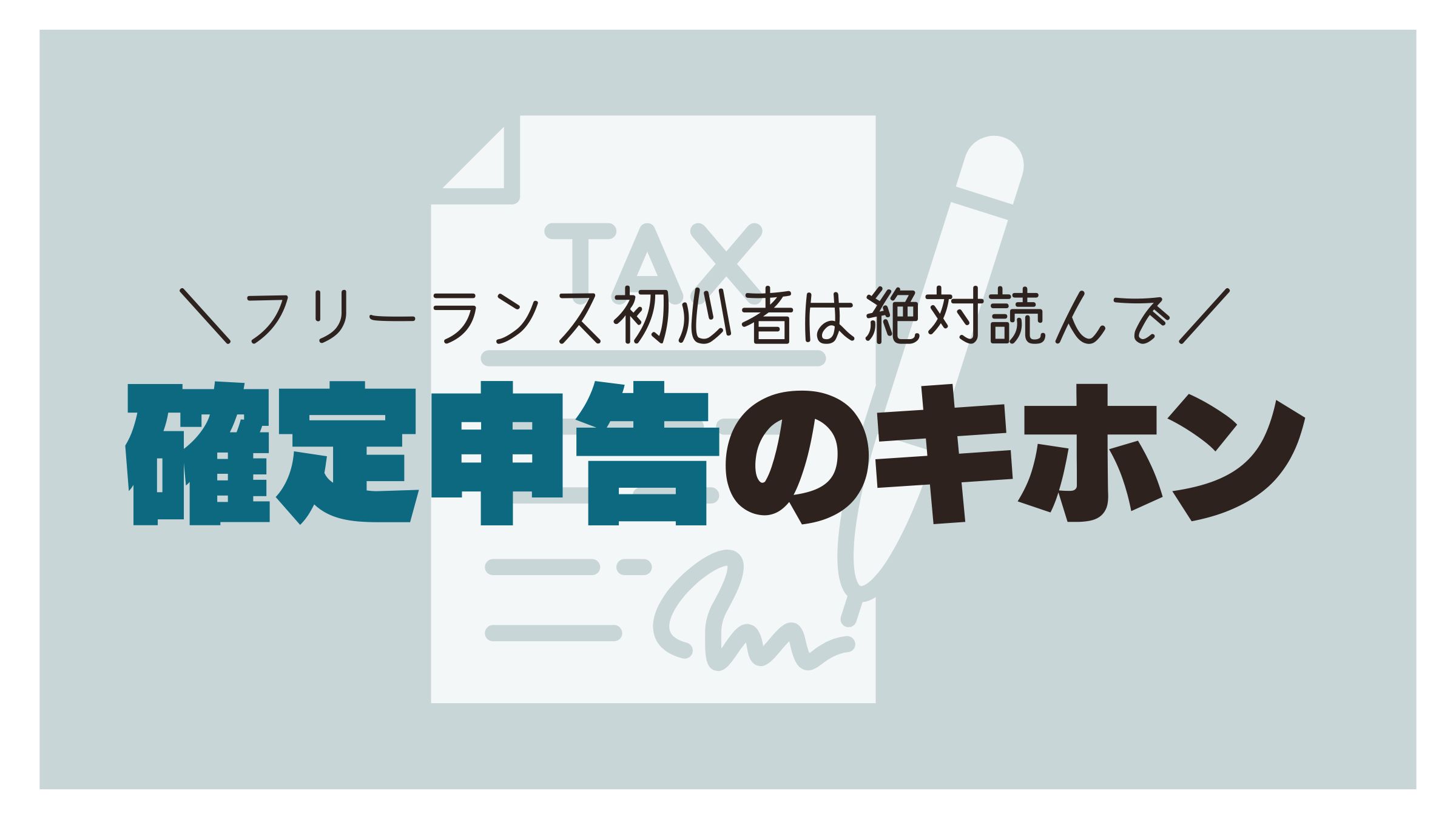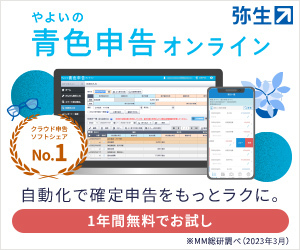会社員として働いていると税金は給料から差し引いて会社が代わりに納めてくれるケースが多いため、普段あまり意識することはないかもしれません。ですがフリーランスは自分で税金を計算し申告して納める必要があり、仕事で得た収入に安心してしまい処理を後回しにすると後々大変なことになる可能性も…。よってフリーランスとして活動するなら、税金にかんする一通りの知識習得が必要不可欠です。
そこでこの記事では、フリーランスにおける税金の基本から節税のポイントまで、初心者にも分かりやすく解説します。後半では確定申告を簡単にする方法もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!
この記事の内容
\読みたい内容をTap・clickでジャンプできます/
この記事を書いた人

西田あずさ
- 在宅で会社を経営する3児の母
- 元貧困シングルマザー
- フリーランス転身で人生大逆転
- スクール/コミュニティ運営(会員400名超)
※本記事の内容は、税理士などの専門家によるアドバイスではありません。実際に確定申告を行う際は、税務署や専門家に相談することをおすすめします。
フリーランスが支払うべき4つの税金
まず、フリーランスに支払い義務が生じる税金は、基本的に以下の4つです。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
以降でそれぞれの税金について簡単に説明しますね。
1.所得税
| 納付先 | 国 |
|---|---|
| 税率 | 課税所得の5%〜45% |
| 納付時期 | 翌年2月16日から3月15日まで |
所得税は、フリーランスのみならず一定額以上の所得がある人全てが納付する必要のある税金です。会社員であれば毎月の給与から「源泉所得税」として天引きされますが、フリーランスは1月1日から12月31日までの所得を基に自身で計算し、原則翌年3月15日までに納付しなければなりません。
税率は売上から経費、各種控除を差し引いた「課税所得」に応じて変動し、所得が多いほど支払う所得税も大きくなる仕組み。加えて、2013年から2037年の期間中は、基準所得税額の2.1%の「復興特別所得税」も併せて納税する必要があります。
課税所得別の所得税額目安
| 課税所得 | 所得税額 | 復興特別所得税額 | 合計納税額 |
|---|---|---|---|
| ¥1,000,000 | ¥50,000 | ¥1,050 | ¥51,050 |
| ¥2,000,000 | ¥10,2500 | ¥2,152 | ¥104,652 |
| ¥3,000,000 | ¥202,500 | ¥4,252 | ¥206,752 |
| ¥4,000,000 | ¥372,500 | ¥7,823 | ¥380,322 |
| ¥5,000,000 | ¥572,500 | ¥12,022 | ¥584,522 |
なお、所得税および復興特別所得税の支払い方法は、原則1年分の一括納税と定められています。会社員のように毎月の収入から天引きされるわけではないので、フリーランスとして活動するなら所得税の支払いを考慮し、期限までにまとまったお金を用意しておきましょう。
2.住民税
| 納付先 | 地方自治体 |
|---|---|
| 税率 | 課税所得の10%+5,000円程度※自治体により異なる |
| 納付時期 | 通常6月〜翌年5月までの分割払い |
住民税は、フリーランスから給与所得者まですべての納税者(一定の事由に該当する方を除く)が住んでいる地域に納める地方税です。こちらも会社員であれば毎月の給与から天引きされて徴収されますが、フリーランスは毎年6月頃に自宅へ届く納付書で自ら納税する必要があります。
住民税は課税所得の原則10%で算出される「所得割」に加え、所得に関係なく均一5,000円程度(自治体により異なる場合がある)の「均等割」と、全国一律1,000円の「定額負担森林環境税」を併せて納税しなければなりません。よってフリーランスが納税すべき住民税は、課税所得の原則10%と定額負担6,000円程度の合計金額です。
課税所得別の住民税額目安
| 課税所得 | 住民税額 |
|---|---|
| ¥1,000,000 | ¥100,000+定額負担 |
| ¥2,000,000 | ¥200,000+定額負担 |
| ¥3,000,000 | ¥300,000+定額負担 |
| ¥4,000,000 | ¥400,000+定額負担 |
| ¥5,000,000 | ¥500,000+定額負担 |
 西田あずさ
西田あずさ所得税とあわせると、課税所得200万円で30万円程度、300万円で50万円程度の税金を納める必要があるということですね!
所得税と同じく自身で納税しないといけないので、フリーランスとして活動するなら住民税納税用の資金をきちんと残しておきましょう。
3.個人事業税
| 納付先 | 地方自治体 |
|---|---|
| 税率 | 3〜5% |
| 納付時期 | 通常8月と11月 |
個人事業税は、対象となる事業を営むフリーランスかつ一定の所得金額を超える場合に課される税金。対象となる事業は全部で70種類以上(※2025年1月時点)あり、幅広い職種が含まれています。
対象となる職業の例
- 物品販売
- Webデザイナー
- 動画編集者
- ライター
- ブログ運営
- オンライン講師
- プログラマー
- エンジニア
事業所得が290万円を超えると課税対象となり、税率は業種により異なるものの通常3%から5%の範囲内で設定されています。個人事業税は事業を行う上での利益に対して課税され、他の税金とは性質が異なるので、詳しく知りたい方はお住まいの地域の税務当局Webサイトや窓口で確認してみてくださいね。
参考:東京都主税局|個人事業税
4.消費税
| 納付先 | 国・地方自治体 |
|---|---|
| 税率 | 8%or10% |
| 納付時期 | 確定申告時 |
消費税は、事業者が消費者から預かった税金を国や地方に納める間接税。フリーランスの場合、年間売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じます。
税率は現在10%(軽減税率対象品目は8%)であり、翌年3月31日までの確定申告時に所得税と同時に納税します。ただし課税事業者には「中間申告・納税」が必要な場合も。その場合は、売上規模に応じて半年または年4回に分けて納付しなければなりません。
なお消費税はフリーランスとして事業を始めたばかりの場合、初年度とその翌年は原則として「消費税免税事業者」として扱われ、消費税の納税義務が免除されます。※開業初年度の上半期(1月~6月)に課税売上が1,000万円を超えた場合を除く



要はフリーランスとして活動を始めて2年は原則消費税を払う必要がないということですね。2年目以降も、年間1,000万円以上売り上げない限り消費税は免税されます!
参考:国税庁|消費税の仕組み
フリーランスにおける税金の金額は確定申告の情報をもとに決まる!
では次にフリーランスの税金がどう決まるのかについて解説していきますが、そもそも納税額は「売上」や「課税所得(売上ー経費ー各種控除)」で決まるものが大半です。なのでまずは国・地方自治体に対しフリーランス自身で収入状況を報告しなければなりません。その手続きが「確定申告」です。
確定申告とは?
前年の所得金額や税額を税務署に申告・納税する手続きのこと。納税対象者(1年間の所得が48万円超え・副業収入が20万円以上などの条件に当てはまる人)は、毎年2月16日頃から3月15日頃までの間に確定申告を行うことが義務化されている。
フリーランスが納める必要のある税金のうち、所得税(及び復興特別所得税)と消費税はこの確定申告時に自ら税額の計算・申告・支払いをすることで納税が完了します。住民税と個人事業税は後日各自治体が支払いを案内してくれるものの、税額を計算してもらうには収入情報の申告が必須。つまり確定申告をしない限りフリーランスが納めるべき税金の金額が決まらず、納税もできません。
期限内に手続きを行わなければ延滞税や無申告加算税といったペナルティを追加請求されることもあるので、納税対象者に該当するフリーランスは毎年必ず確定申告を行いましょう。
確定申告の詳しい知識はこちら
参考:国税庁|所得税の確定申告
税金を支払いすぎないようにフリーランスがやるべきこと
これまで解説したとおり、フリーランスは課税所得200万円前後でも最低30万円ほどの税金を納める必要があり、対象者である限り支払いからは逃れられません。とはいえ、できるだけ納税額は少なく済ませたいのが本音ですよね。そこでここからは、税金の負担を軽減するために身につけておくべき知識を確認していきましょう。
- 必要経費を漏れなく計上する
- 青色申告を利用する
- 控除を活用する
1.必要経費を漏れなく計上する
フリーランスが支払うべき税金は「所得」が多いほど高額が高くなるものがほとんどです。ただ「所得」とは売上から“必要経費”を差し引いたもの。税金の負担を軽減するには、事業運営のために使ったお金を漏れなく計上しましょう。
経費計上できる費用の例
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 交際費 | 顧客との会食費 取引先へのお歳暮・お中元費 |
| 家賃・光熱費 | 事務所の家賃・光熱費 自宅の家賃・光熱費の一部※自宅を事業所にしている場合 |
| 交通費 | 仕事で使ったタクシー代 仕事で使った車のガソリン代 |
| 通信費 | 仕事用のスマホ利用料金 自宅のインターネット代の一部※自宅を事業所にしている場合 |
| 広告費 | 仕事のためのブログ運営費 名刺の作成費用 |
| 勉強・研修費 | スキルアップのための講座受講費 業務に関連する書籍代 |
| 消耗品費 | 事務用品代 事務所のトイレットペーパー代 |
| 仕事用機材の購入費 | 業務で必要なパソコン代 打ち合わせで使うWebカメラ代 |
上記はほんの一例であり、事業運営・売上アップのために使った費用は基本的に全て経費として計上が可能。例えば、仕事をするためにカフェに入ったならその飲み物代、集客を目的としたオンラインセミナー出演のために洋服を購入したならその代金なども計上できるでしょう。何でも経費計上していいわけではないものの、仕事で使ったお金は普段から正確に記録し申告時にきちんと計上することが、適正金額の納税につながります!
なお申告した経費を認めてもらうには、その証拠として原則領収書やレシートが必須。確定申告時の提出は不要ですが、万が一税務調査が入った場合は1つずつ確認されることがあるほか、最低でも5年間の保管が義務付けられています。経費計上するなら、領収書やレシートも必ず保管しておきましょう。
2.青色申告を利用する
続いてフリーランスが必ず取り入れたい節税対策のひとつが「青色申告」の利用です。青色申告とは確定申告で複式簿記等の方法により記帳することで特別控除を受けられる申告制度のこと。実は確定申告には2種類の申告方法があり、どちらを選択するかにより受けられる控除額が異なります。
確定申告の種類
| 種類 | 控除額 |
|---|---|
| 白色申告 | 0円 |
| 青色申告 | 最大65万円 |
所得税や住民税の基準となる「課税所得」は売上から必要経費、各種控除額を差し引いて算出されるので、控除額が大きければその分課税対象となる所得を減らせます。青色申告は白色申告に比べ帳簿管理や申告手続きがかなり面倒ですが、最大65万円もの控除を受けられるなら利用しない手はありません。



他に、赤字を3年間繰り越しできたり、パソコンなどを購入した場合に一括で経費にできる金額がアップりたり…メリットが豊富です!
ただし、青色申告を利用するには「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が欠かせません。いずれも税務署で手続きできるので、フリーランスになったのであれば早めに提出しておくと良いでしょう。
参考:国税庁|青色申告制度
3.控除を活用する
青色申告の他にもフリーランスが受けられる控除は多々あり、それらを活用すればさらなる節税効果が見込めます。ただし控除は全てが自動的に適用されるわけではありません。自身が受けられる控除はしっかり把握し、確定申告の際にきちんと申告できるようにしておきましょう。
主な控除
| 控除の種類 | 概要 | 控除額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | すべての納税者に適用 | 一律48万円 |
| 扶養控除 | 扶養家族がいる場合に適用 | 最大63万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者の収入が一定額以下の場合に適用 | 最大38万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親で所得が一定以下の場合に適用 | 35万円 |
| 生命保険料控除 | 生命保険の支払いに対して控除を適用 | 所得税:最大12万円 住民税:最大7万円 |
| 医療費控除 | 年間の医療費が一定額を超える場合に控除可能 | 最大200万円 |
| iDeCo | 老後資金形成のための制度で、利用している場合に掛金を全額所得控除可能 | 年間14.4~81.6万円※職業により異なる |
| 小規模企業共済 | 退職金制度の一環で、利用している場合に掛金を全額所得控除可能 | 年間84万円まで |
| 寄付金控除 | 寄付金(ふるさと納税含む)が対象になる場合に適用 | 寄付金額-2,000円 |
特別なことをしなくても適用される控除はいくつかあるはずですが「iDeCo」や「小規模企業共済」など自分にメリットがありなおかつ控除対象である制度も、積極的に活用してみると良いでしょう。これらを利用すれば、税負担を軽減しながら将来の資金形成や家庭の経済的負担サポートにつながります。



控除の種類・細かな適用条件などは国税庁のWebサイトや税務署の窓口でぜひ確認しておいてください!
フリーランスが過不足なく正しい納税を行うなら「会計ソフト」の導入がおすすめ!
フリーランスにおける税金の知識について紹介しましたが、できる限りの節税をしたうえで自分が支払う必要のある税金を過不足なく納めるには、前提として“正しい確定申告”が必須です。しかし確定申告には簿記や会計の知識がある程度必要であり、日頃の収支を漏れなく記録&記帳したうえで自ら税額の計算もしなければなりません。特別控除を受けられる青色申告を利用する場合は複雑な帳簿付けが必須なので、なおさら難しい作業を要します…。



そこで正確かつ簡単に納税を行うためにフリーランスが絶対活用すべきなのが「会計ソフト(確定申告ソフト)」です!
会計ソフト(確定申告ソフト)とは、案内に従って必要な情報を入力するだけで、確定申告に必要な各種書類を作成したり、帳簿を作ったりしてくれるソフトウェアのこと。大半のソフトが、銀行口座やクレジットカードと連携することで売上や経費の支出といった取引データの自動取得・仕訳・帳簿付けにも対応しています。適用される控除なども自動で案内してくれるので、知識がないゆえに本来支払うべき税金より多く納税してしまうことも防げるでしょう。つまり会計ソフトを導入しておけば、簿記や会計の知識がなくてもフリーランスに必要な経理作業が正確かつ簡単に完結するのです。
なお代表的なソフトは以下の3つ↓
これらは全てWeb上で使えるうえ、月額約1,000円〜で利用可能。作成した書類の電子申告(e-Tax)にも対応しており、申告時に自宅から出る必要もありません。節税につながる青色申告をするならもはやソフトの利用は必須かなと思うので、比較検討したうえでの導入をおすすめします!
会計ソフトについての詳細・比較はこちら
まとめ:フリーランスは正しい税金の知識を身につけておこう
以上、会社員とは違い、フリーランスは税金にかんしても自ら責任を持ち適切に処理する必要があります。納税は国民の義務ですから「知らなかった」ではすみません。
フリーランスとして生きていくのであれば支払うべき税金はしっかり把握し、過不足なく納税しましょう。
「正確かつ効率的に確定申告したい!」「会計作業について全く分からない…」という方は確定申告ソフトの導入もぜひ検討してみてくださいね。